先日、高速道路を走っていたら前の車がオービスでパシャっと光られているのを目撃してしまいました...。
その時ふと「オービスって一体何キロオーバーで光るんだろう?」と疑問に思ったんです。
そこで今回は、オービスについて徹底的に調べてみることにしました!
オービスが光る速度や、実は結構種類があることなど、知られざるオービスの雑学をまとめてみます。
安全運転の参考にもなると思うので、ぜひ最後まで読んでみてください。
オービスが光る速度について
基本的な作動条件
まず気になる「何キロで光るのか」について。
実は、オービスには明確な公開基準はないのですが、一般的に言われている目安があります。
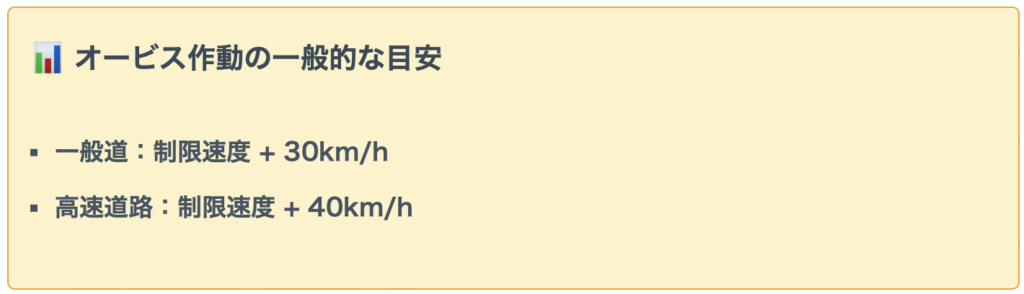
例えば、制限速度50km/hの一般道なら80km/h以上、
制限速度100km/hの高速道路なら140km/h以上で作動する可能性が高いとされています。
なぜこの基準なのか?
この基準は「赤切符(一発免停)」の速度違反基準と関連しています。
赤切符の基準も一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過なんです。
地域や路線による違い
ただし、これはあくまで目安。実際には以下のような要因で作動基準が変わることがあります。
- 事故多発地点では、より低い速度で作動することがある
- スクールゾーンや住宅密集地では厳しく設定される場合がある
- 時間帯による調整が行われることもある
〜重要な注意点〜
これらは一般的に言われている目安であり、実際の作動条件は公開されていません。
安全運転のため、制限速度を守ることが最も大切です!
オービスの種類を徹底解説
実は、オービスって結構いろんな種類があるんです。それぞれ特徴が違うので、詳しく見ていきましょう。
1. ループコイル式オービス
特徴:道路に埋め込まれたセンサーで速度を測定
- 路面に四角い枠のような跡が見える
- 最も古い方式で、精度が高い
- 設置・メンテナンスにコストがかかる
- 主要幹線道路や高速道路に多い
2. レーダー式オービス
特徴:電波(マイクロ波)を使って速度を測定
- 上空からマイクロ波を照射
- レーダー探知機で検知される可能性が高い
- 設置が比較的簡単
- 天候の影響を受けにくい
3. 光電管式オービス
特徴:赤外線ビームで車両の通過時間を測定
- 道路脇に光電管(赤外線センサー)を設置
- レーダー探知機では検知できない
- 比較的古い技術だが、まだ現役
- 一般道に多く設置されている
4. Hシステム(ハイブリッド式)
特徴:レーダーと光電管を組み合わせたシステム
- 2つの方式の利点を組み合わせ
- 精度が非常に高い
- 比較的新しいシステム
- 主要道路での導入が進んでいる
5. LHシステム(移動式オービス)
特徴:持ち運び可能な小型システム
- 三脚で設置する可搬型
- 設置場所が事前に分からない
- 生活道路や事故多発地点で活用
- 最も新しいタイプで導入が拡大中
見分け方のポイント
運転中に「あ、これオービスだ」と分かるポイントをまとめてみました。
共通の特徴
- 「自動速度違反取締装置設置路線」の看板が手前にある
- 大型のカメラとフラッシュ装置が設置されている
- 路面にセンサー跡がある(ループコイル式の場合)
タイプ別の見分け方
- ループコイル式:路面に四角い継ぎ目、大型の機械
- レーダー式:上部にレーダーアンテナが見える
- 光電管式:道路脇に小さなセンサーが複数
- 移動式:三脚に設置された小型カメラ
まとめ:安全運転が一番大切
今回オービスについて調べてみて、改めて思ったのは「やっぱり制限速度を守るのが一番」ということです。
オービスの設置場所や作動条件を知ることは興味深いですが、それよりも大切なのは、
制限速度を守る・周囲の交通状況に注意を払う・歩行者や自転車に配慮する・疲労時の運転を避ける
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
他にも車関係の雑学記事を書いていく予定なので、また遊びに来てくださいね~